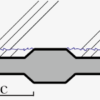この記事ではコンクリートと鉄筋の許容応力度について紹介します。
許容応力度とは、構造物に想定されるいろいろな外力に対して発生する応力にどれだけ耐えられるかを示す値です。許容応力度が大きければ大きいほど、その構造物は大きな応力に耐えることができます。
では早速コンクリートと鉄筋の許容応力度を紹介していきましょう。
コンクリートの許容応力度
コンクリートの引張応力度は0として考えます。コンクリートが引張応力度を負担することは想定されていません。コンクリートのような構造材料の許容応力度は学会で定められており、設計時の基準となります。
ではコンクリートの許容応力度を表で確認します。単位は[N/mm²]です。
| 種別 | 長期許容応力度 | 短期許容応力度 | ||
| 圧縮 | せん断 | 圧縮 | せん断 | |
| 普通コンクリート | Fc/3 | min(Fc/30, 0.49+Fc/100) | 長期許容応力度の2倍 | 長期許容応力度の1.5倍 |
| 軽量コンクリート | Fc/3 | 普通コンクリートの0.9倍 | ||
Fcとは、コンクリートの設計基準強度です。構造設計時に計算されるコンクリートの圧縮に対する強度のことをさします。建築構造材料には他にも木材などのいろいろなものありますが、それぞれの材料に基準強度というものが定められています。
上の表の普通コンクリートの長期せん断許容応力にあるmin(Fc/30, 0.49+Fc/100)は、Fc/30と0.49+Fc/100の小さい方を許容応力として扱うという意味になります。
長期と短期の違いですが、こちらは建築基準法で長期と短期の区別がされており、長期は50年間以上、短期はそれ以下の期間で構造物が利用されることを想定されています。
鉄筋の許容応力度
次に鉄筋の許容応力度を紹介します。コンクリートと鉄筋が併用される(鉄筋コンクリートとして使用される)場合は、鉄筋の長期許容応力度はコンクリートの最大ひび割れ幅が0.3mm以下になるように安全率が設定されています。安全率に関しては以前まとめた記事がありますので、気になる方はそちらをご覧ください。
では鉄筋の許容応力度の表を見ていきましょう。単位は[N/mm²]です。
| 種別 | 長期許容応力度 | 短期許容応力度 |
| SD295A | 196 | 295 |
| SD345 | 215 | 345 |
SD295AとSD345は鉄筋の種類の名前です。これらの名前は鉄筋材料の記号で種類を表しています。鉄筋の種類と名前に関しては以下の記事を参考にしてください。
鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度
最後に鉄筋とコンクリートに対する許容付着応力度に関して紹介します。鉄筋とコンクリートの付着とは、鉄筋コンクリートとして使用される際に、鉄筋とコンクリートがどれだけ一体化しているかを示す値になります。鉄筋とコンクリートの付着の仕組みや鉄筋の付着によるコンクリートの破壊現象についてまとめた記事もありますので、合わせて読むと理解が深まります。
鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度とは、鉄筋コンクリートがどれだけ一体性を持って応力に耐えることができるかを表します。つまり許容付着応力度を超えてしまうと、鉄筋とコンクリートがズレてしまい、鉄筋コンクリートとしては劣化してしまうということです。
鉄筋の位置によって許容応力度に差があるため、針の上端筋は許容応力度が小さく設定されています。実際に付着応力度を表で見てみましょう。単位は[N/mm²]です。
| 種別 | 長期許容付着応力度 | 短期付着応力度 | |
| 梁の上端 | 左記以外の位置 | ||
| 異形鉄筋 | min(Fc/15, 0.9+cFc/75) | min(Fc/10, 1.35+Fc/25) | 長期許容付着応力度の1.5倍 |
まとめ
今回はコンクリートと鉄筋の許容応力度、それから鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度に関して紹介しました。これらの数値を厳格に覚えることは難しいですが、だいたいの値を覚えておけば頭の中で構造計算をすることがスムーズにできます。実際の構造計算では許容応力表などを用いて計算するでしょう。
今回の記事は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。